仕事や日常において、「モチベーションはどうやって保てば良いか」という問題に直面することが多いと思います。
これは誰にとってもありがちで、なかなか解決のし難い問題ですよね。
ただ実はこのモチベーションに関しても、心理学が深く関わっています。
そして心理学を踏まえることで
- なぜ、モチベーション維持が難しいのか
- モチベーションを保つにはどうすれば良いか
の答えが見えてきます。
今回の記事は以下の方向けになります。
- モチベーション管理して成果につなげたい
- 自分の中で習慣化したいことがある
- 子供や部下のやる気を引き出したい
「継続は力なり」ー さっそく心理学の知見を紹介するので、モチベーションのコツについて見ていきましょう!
モチベーションの鍵:期待理論とは?
モチベーションの鍵:期待理論とは?
心理学においても、働きからや個人の自己啓発の心理を研究する産業心理学において、期待理論というものがあります。
これは心理学者のヴルーム氏によって提唱されたもので、様々な組織で参考にされています *1)
期待理論によると、モチベーションは、課題への期待性 × 道具性 × 誘意性で決まるというものです。
例えば資格勉強を例にあげて、それぞれの性質を見ていきます。
- 期待性:勉強を続ければその資格が取れる見込みがあるか
- 道具性:資格によって、次のステップにつながる要素があるか(転職への有利性、スキルアップ)
- 誘意性:資格取得によって得られる報酬があるか(会社での評価、自信の向上など)
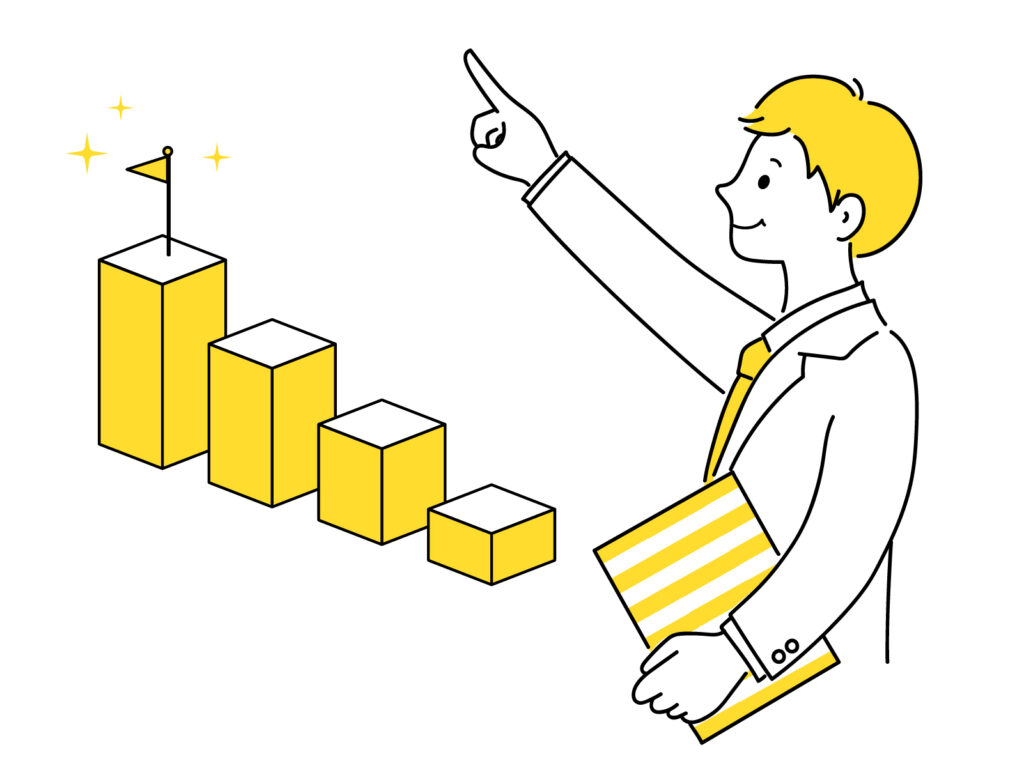
モチベーションはそもそも沸きにくいものだから、管理が大事
この3要素の性質は、各要素は掛け算であるため、どれかが欠けているとモチベーション維持は困難という事になります。
モチベーション管理が誰にとっても大変なのは、この3要素が0にならないよう管理する必要があるからと言えるでしょう。
また一方で、この3要素のスコアがそれぞれ高ければモチベーションは急激に上がることも意味しているのです。
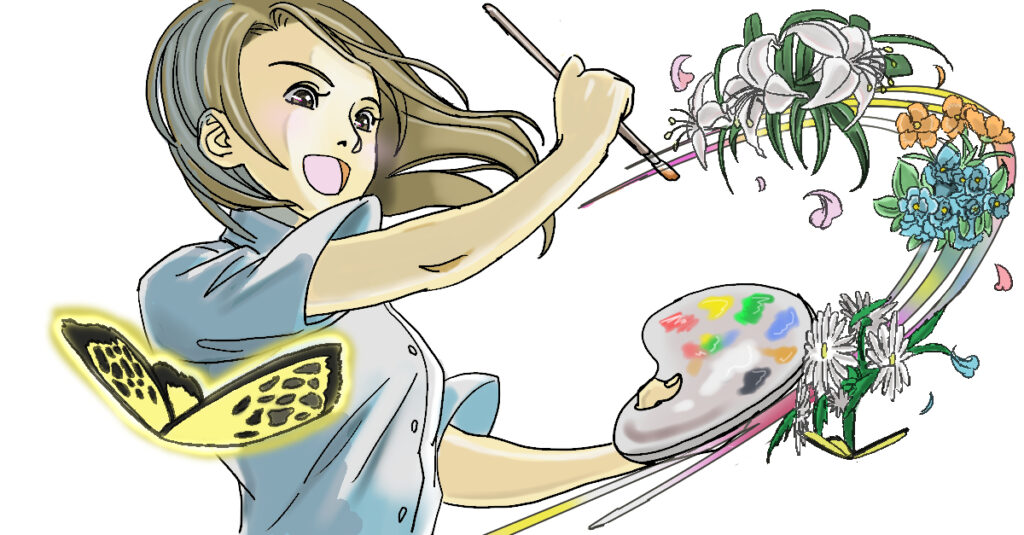
例えば、爆発的にやる気が出る経験はこういう場合に該当しますね。
もしかしたら心当たりのある方もいるかもしれません。
モチベーション管理は難しいからこそ、コントロール次第で差がつきやすいと言えます。
継続の鍵は、モチベーションの性質と上手に付き合っていくかになってくると思います。
【目標設定理論】効果的な目標を立てて良いスタートを!
では、期待理論の3要素をそれぞれ上げていくにはどうすれば良いでしょうか。
まずは目標設定が必要となってくると思いますが、ここでも心理学がヒントになります。
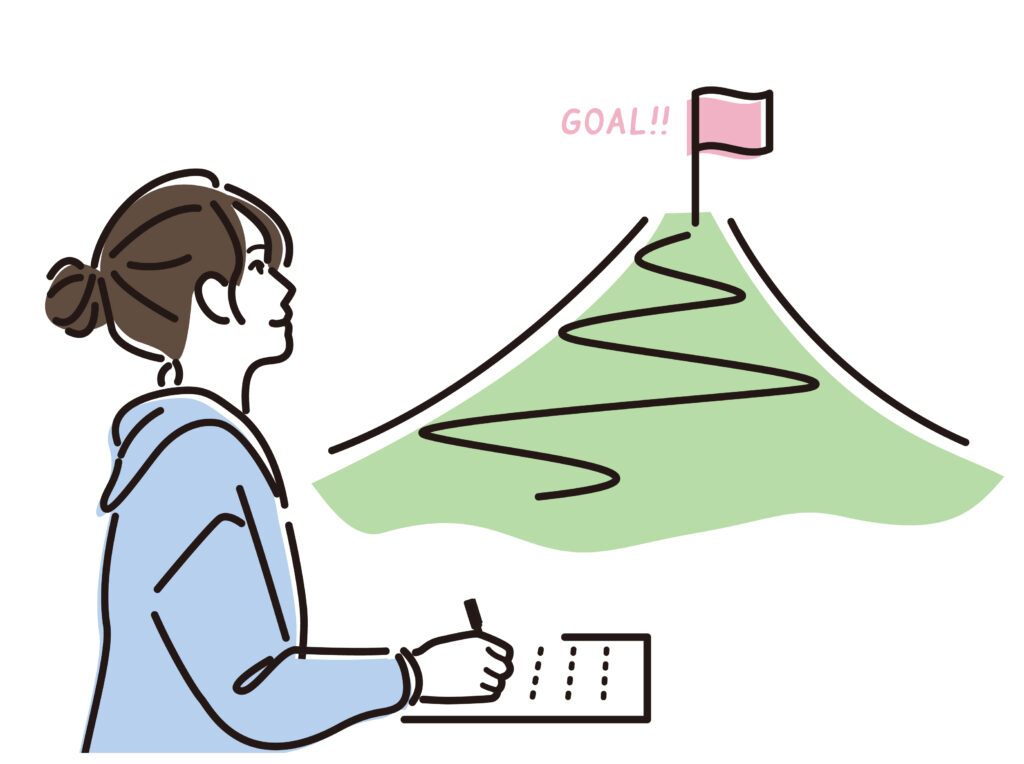
産業心理学において、アメリカの心理学者ロックが目標設定理論というものを提唱しています。*2)
これは色々なところで解説がされていますが、まとめると以下の3つに集約されます。
- 具体的な目標
- 目標へのコミットメント
- 難しさの明確化
以下で一つづつ見ていきたいと思います。
具体的な目標
まず具体的な目標を立てるためには、数値化するなどして到達ラインを明確にすることです。
方法としてはSmartモデルを使って目標を具体的で現実的、かつ挑戦的なものへしていきます。*3)
さらに、先程の期待理論の各3要素をいい感じに散りばめて、モチベーションの上がりやすい目標へ仕上げていきます。
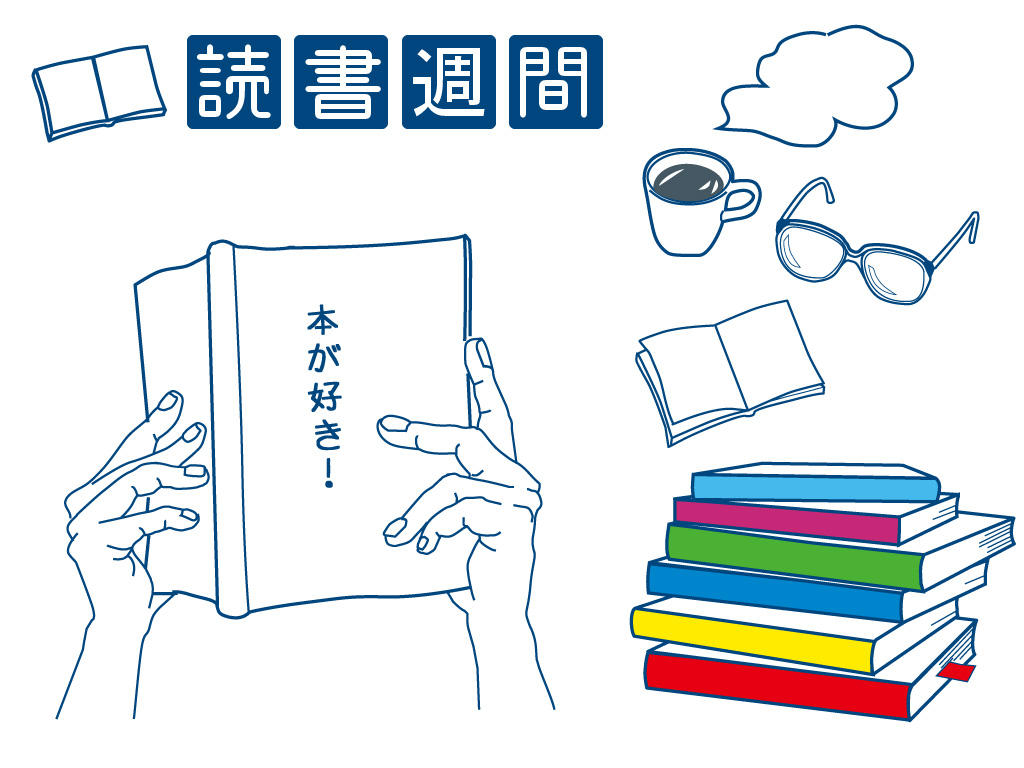
具体的な目標設定の例:読書の習慣を身につける目標設定の例 ① SmartのS(具体性) ・読書の習慣づけのため、まずは3ヶ月間は月に1冊、次の3ヶ月では月に2冊の本を読む。 ・道具性を上げるために、読むジャンルを工夫する(仕事に関係する本か、教養とスキルアップの両方を身につけられる本を選んでみる) ② SmartのM(測定可能な) ・感想をSNSに投稿して読書記録にすることで、主観的にできていることを確かめられるようにする。 ・SNS投稿で読書仲間を増やすことができ、誘意性を上げられる ③ SmartのA(挑戦的) 挑戦的で誘意性のある目標とするために、目標の副題として ・本を読み終わったらそれを読書会で発表してみる ・速読力を高める ・知り合いに読書が趣味と言えるようにする ④ SmartのR(現実性) 今までは2月に1冊ペースだったので、これを月1冊ペースで習慣的に毎日少しづつ読むなら実現可能と判断し、期待性を意識した ⑤ SmartのRT(期日) 半年後に、実績的にも意識的にも習慣づいた状態にする
目標へのコミットメント
目標へのコミットメントとは、自分が立てた目標への関わりを強くすることです。
コミットメントもすでに色々な所で解説されていますが、主に
「周囲への公言」や「責任の意識」で強めることができます。

コミットメントを意識した目標設定の例
【生活習慣の改善の例】
例えば禁煙が目標なら、周囲にそれを公言して目標への意識付けを強化する
【資格の取得】
・資格取得により自分の専門性の裏付けになり、会社の売り上げ向上にもつながるため、目標面談で事業への貢献度を踏まえて説明することで、意識づけを強化した。
・加えて今後の評価に関わる目標面談で公言することで、目標への誘意性を上げた
難しさの明確化
最後に難しさの明確化ですが、目標は高すぎると挫折しやすく、逆に簡単すぎると退屈してしまいます。

これは、難しすぎる目標では期待理論の「期待性」が下がり、簡単な目標では「道具性」と「誘意性」が下がってしまうためです。
そこで、目標において何が難しいかを取り入れて、程よい難易度のある目標へ仕上げていきます。
難易度を取り入れた目標設定の例 ・事務作業の目標設定 事務作業で伝票を今月は100件処理する目標を立てたが、単純な物量だけだと目標に難しさが含まれない。 そこで、「100件のうち10件は自分が未経験で少し難しい会計取引の伝票を処理できるようにする」という目標にした ・整理整頓の習慣づけ 苦手だった整理整頓を習慣づけるため、毎日10分は整理整頓の時間を設けるようにした。 しかしそこに挑戦しがいがないため、ネットで調べた整頓術を3つ以上身につける目標を追加した。
期待理論を軸に、色々なモチベーション管理方法を取り入れてみる
今回は目標設定におけるSmart法則や、コミットメントの強化などの方法を説明しました。
もちろん他にも様々な方法があると思います。
まずはモチベーションの3要素(期待性・道具性・誘意性)を上げる為に、色々な手法を工夫して取り入れて、モチベーション管理を進化させていくと楽しみながらできるかもしれませんね。
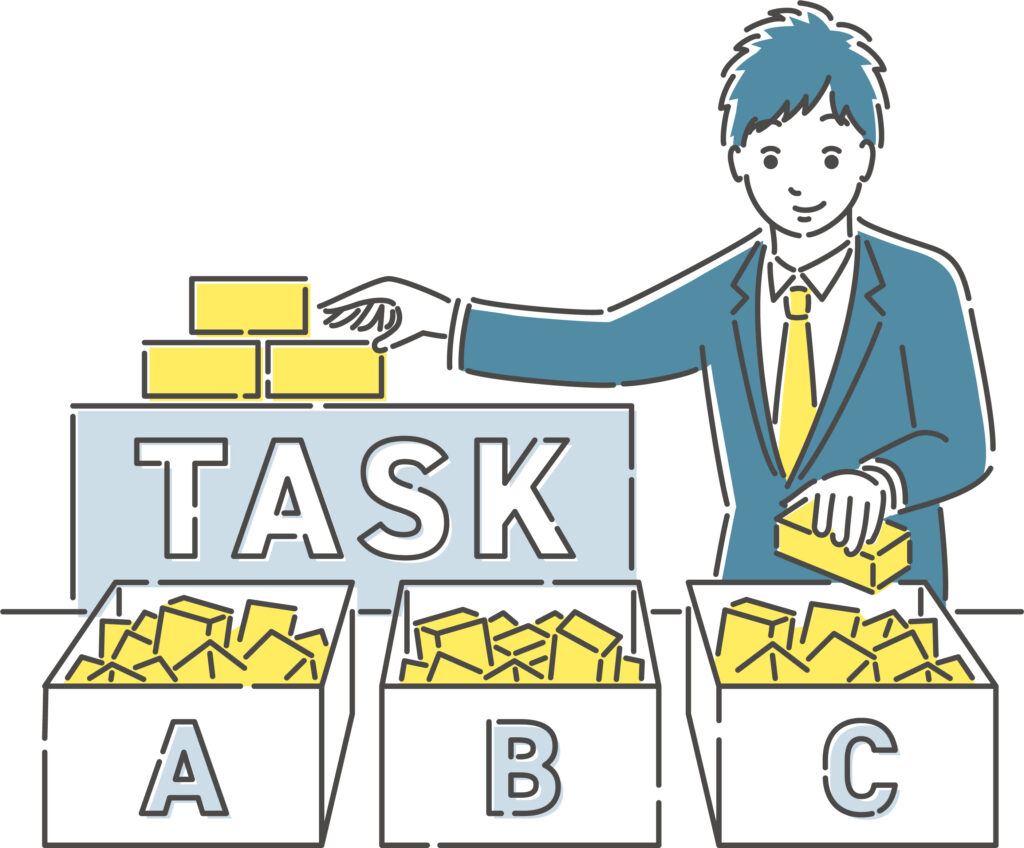
参考リンク
*1) 期待理論
https://www.ashita-team.com/jinji-online/development/10361#i
https://www.paddledesign.co.jp/point/post-167.html
*2) 目標設定理論
https://jinjibu.jp/keyword/detl/1454/
https://jp.indeed.com/career-advice/career-development/goal-setting-theory
https://ua-book.shop-pro.jp/?pid=159283746
*3) 目標設定におけるSmartの法則
https://www.kaonavi.jp/dictionary/smart-criteria/



コメント